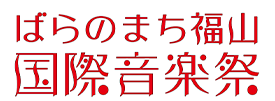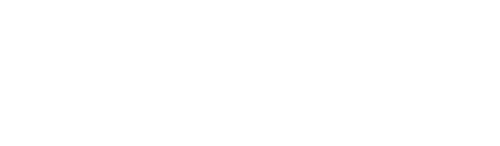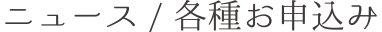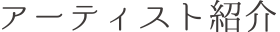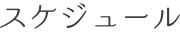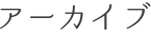ハンギョン・アルテ・フィルハーモニック(管弦楽) Hankyung arte Philharmonic (Orchestra)
ハンギョン・アルテ・フィルハーモニックは、「文化と経済の架け橋」をスローガンに、2015年9月に韓国経済新聞社によって設立された。韓国を代表するマエストロ、グン・ナンセが初代音楽監督として2018年8月まで楽団を率い演奏レヴェルを格段に引き上げ、その後韓国の著名な指揮者が次々と客演指揮している。2019年以来、オーストリア・インスブルックのチロル州立劇場の第1首席指揮者をつとめたホン・ソクウォンが第2代音楽監督に任命された。交響曲・管弦楽曲だけでなく、オペラ・声楽曲も韓国国立歌劇場・合唱団などと演奏しレパートリーを更に充実させており、青少年のためのコンサート、春の音楽コンサート、メモリアル・コンサート、夢の教科書コンサートなどさまざまな演奏会を行って韓国のクラシック音楽シーンで確固たる地位を築いている。

ヨンミン・パク(指揮) Youngmin Park (Conductor)
韓国ソウル生まれ。ソウル大学で作曲と指揮を学んだ後、ザルツブルク・モーツァルテウム大学にてミヒャエル・ギーレンに学び首席で卒業。さらにイタリアのシエナ・キジアーナ音楽院にてチョン・ミュンフンに師事した他、ニコラウス・アーノンクールの下でも研鑽を積んだ。プラハのドヴォルザークホールでドヴォルザークの交響曲でデビューを果たした後、ウィーン楽友協会のブラームスザールでハイドンの交響曲を指揮し、いずれも成功をおさめている。客演指揮者としてヨーロッパの様々なオーケストラを指揮しているほか日本ではオーケストラ・アンサンブル金沢なども振っている。ソウル・クラシカル・プレイヤーズの音楽監督・常任指揮者、ウォンジュ・フィルの首席指揮者などを歴任し、チュゲ芸術大学にて後進の指導にもあたっている。国際モーツァルト財団のパウムガルトナー賞を受賞。

バリー・ダグラス(ピアノ) Barry Douglas (Piano)
1986年チャイコフスキー国際コンクールに優勝して以来、国際的な演奏活動を繰り広げている。1999年には南北アイルランド出身の演奏家で構成される室内アンサンブル、カメラータ・アイルランドを結成し、芸術監督を務めている。これまで、ロンドン響、BBC響、ボルティモア響、ヘルシンキ・フィル、ドレスデン・フィル、ハレ管、ベルリン放送響などと共演。フランス、アイルランド、イギリス、アメリカ、ドイツ、ロシアでは定期的にリサイタルに出演している。最近は指揮者(弾き振り) としての評価も高まっており、アカデミー室内管、インディアナポリス響、バンクーバー響、モスクワ・フィルなどとの共演はいずれも絶賛を博す。2002年、音楽への貢献で大英帝国勲章(OBE)を受章。

ジュハ・チェ(ヴァイオリン) Jooha Cho(Violin)
2002年生まれ。ソウル芸術高校で学び、第62回東亜音楽コンクールで優勝しウゴム賞受賞、香港次世代アーツ国際コンクール第2位、第35回釜山音楽コンクール第1位など、国内外の数多くのコンクールで優勝、最高賞を受賞しているほか大阪国際音楽コンクール・アンサンブル部門で審査委員長賞、エスポワール賞を受賞。クムホ・ヤング・アーティスト・コンサート(錦湖文化財団主催)、ソンナム・フィルハーモニー管弦楽団の定期公演にも出演している。現在はソウル大学音楽学部で奨学生として、ジオン・ベク教授に師事している。2023年IMA音楽賞受賞。

大阪交響楽団 Osaka Symphony Orchestra
1980年「大阪シンフォニカ-」として創立。初代音楽監督・常任指揮者に小泉ひろしを迎える。 創設者である、永久名誉楽団代表・敷島博子が『聴くものも、演奏するものも満足できる音楽を!』を提唱。いつも聴衆を“熱く”感動させるその演奏は、「魂の叫び」「情熱の音」と評されている。
2001年1月に、楽団名を「大阪シンフォニカ-交響楽団」に、2010年4月「大阪交響楽団」に改称した。
1992年1月にトーマス・ザンデルリンクを音楽監督・常任指揮者に迎え、オーケストラとしての基礎を築いた。その後、曽我大介、大山平一郎、児玉宏、外山雄三の歴代シェフのもと、楽団は大きく発展を遂げてきた。また、2022年4月、新指揮者体制として、山下一史(常任指揮者)、柴田真郁(ミュージックパートナー)、髙橋直史(首席客演指揮者)の3名が就任、さらなる楽団の飛躍が期待されている。
2006年4月、大和ハウス工業株式会社 代表取締役会長 CEO(当時) 樋口武男氏が運営理事長を経て、2018年11月公益社団法人大阪交響楽団理事長に就任。2020年10月に大和ハウス工業株式会社 代表取締役社長 CEO 芳井敬一氏に理事長をバトンタッチした。
楽団公式ホームページ(https://sym.jp)(2022年4月現在)

柴田真郁(指揮) Maiku Shibata (Conductor)
1978年東京生まれ。国立音楽大学声楽科を卒業後、合唱指揮やアシスタント指揮者として藤原歌劇団、東京室内歌劇場等で研鑽を積む。
2003年に渡欧、ドイツ各地の劇場、オーケストラで研鑽を積みながら、04年にウィーン国立音楽大学マスターコースでディプロムを取得。修了演奏会でヴィディン・シンフォニーオーケストラ(ブルガリア)を指揮した。同年末には、ハノーファー・ジルベスター・コンサート(ドイツ)に客演し、プラハ室内管弦楽団を指揮。翌年末のベルリン室内管弦楽団にも客演、2年連続でジルベスターコンサートを指揮して大成功を収める。
2005年、リセウ大歌劇場(スペイン・バルセロナ)のアシスタント指揮者オーディションに合格し、セバスティアン・ヴァイグレ、アントーニ・ロス=マルバ、レナート・パルンボ、ジョセップ・ヴィセント氏等のアシスタントとして、様々な演出家や歌手と携わり上演で大きな信頼を得た経験は、オペラ指揮者としての礎となっている。
帰国後は主にオペラ指揮者として活動し、2010年、池辺晋一郎「死神」で日本オペラ協会にデビュー。同年、五島記念文化財団オペラ新人賞を受賞して研修生として再度渡欧し、イタリアの劇場を中心に研鑽を積んだ。
最近では18年にマスネ「ナヴァラの娘」(日本初演)、19年にプッチーニ「ラ・ボエーム」、20年にはヴェルディ「リゴレット」、21年にはベッリーニ「清教徒」をそれぞれ藤原歌劇団と共演。20年11月には日生劇場にて「ルチア~あるいはある花嫁の悲劇~」も指揮し、好評を博す。堺シティオペラ、新国立劇場オペラ研修所等でも指揮。しなやかでありながらドラマティックな音楽作りには定評がある。
近年では管弦楽にも力を入れており、読響、東響、東京フィル、日本フィル、神奈川フィル、名古屋フィル、日本センチュリー響、大響、群響、広響、兵庫芸術文化センター管等を指揮。
指揮を十束尚宏、星出豊、ティロ・レーマン、サルバドール・マス・コンデの各氏に師事。平成22年度(2010年)五島記念文化財団オペラ新人賞(指揮)受賞。2022年4月、大阪交響楽団ミュージックパートナーに就任。

堀米ゆず子(ヴァイオリン) Yuzuko Horigome (Violin)
5歳からヴァイオリンを久保田良作氏のもとで始め、1975年より江藤俊哉氏に師事。1980年桐朋学園大学卒業。同年エリーザベト王妃国際音楽コンクールで日本人初の優勝を飾る。以来ベルリン・フィル、ロンドン響、シカゴ響、クラウディオ・アバド、小澤征爾、サイモン・ラトルなど世界一流のオーケストラ、指揮者との共演を重ねている。
世界中の音楽祭に数多く招かれ、その中にはアメリカのマールボロ音楽祭、クレーメルの主宰するロッケンハウス音楽祭、ルガーノアルゲリッチ音楽祭(スイス)、フランダース音楽祭(ベルギー)などがある。室内楽にも熱心に取り組んでおり、これまでにルドルフ・ゼルキン、アルゲリッチ、ルイサダ、クレーメル、マイスキー、今井信子、メネセス、ナイディックなどと共演している。2013年からイタリアのカメラータピチュナに於いて、2014年からはイギリスのケンブリッジに於いてマスタークラスを2017年まで開催した。2018年からはフランスのエクサンプロヴァンスでマスタークラスを開催している。

佐藤晴真(チェロ) Haruma Sato (Cello)
2019年、ミュンヘン国際音楽コンクール チェロ部門において日本人として初めて優勝。18年にはルトスワフスキ国際チェロ・コンクール第1位および特別賞を受賞。第83回日本音楽コンクール チェロ部門第1位および徳永賞・黒柳賞など受賞多数。国内外の主要オーケストラと共演しており、リサイタル、室内楽でも好評を博している。20年、名門ドイツ・グラモフォンよりデビューアルバムをリリースし、23年4月には3枚目のアルバムとなる『歌の翼に~メンデルスゾーン作品集』をリリースした。第18回齋藤秀雄メモリアル基金賞、第30回出光音楽賞、第32 回日本製鉄音楽賞受賞。21年度文化庁長官表彰(国際芸術部門)。使用楽器は宗次コレクション貸与のE. ロッカ1903年。

津田裕也(ピアノ) Yuya Tsuda (Piano)
仙台市生まれ。東京藝術大学、同大学院修士課程を経て、ベルリン芸術大学で学ぶ。07年仙台国際音楽コンクールにて第1位、および聴衆賞、駐日フランス大使賞を受賞。11年ミュンヘン国際コンクール特別賞受賞。
ソリストとして日本各地のオーケストラと共演するほか、東京・春・音楽祭、仙台クラシックフェスティバル、武生国際音楽祭、木曽音楽祭などに定期的に招かれる。室内楽活動にも積極的で、多くの著名な音楽家と共演を重ねる。特に、白井圭(vn)、門脇大樹(vc)とはトリオ・アコードを結成し、国内各地で演奏。
パスカル・ドヴァイヨン、ガブリエル・タッキーノ、ゴールドベルク山根美代子、角野裕、渋谷るり子の各氏に師事。東京藝術大学准教授。

シャロン・キム(ソプラノ) Sharon Kim(Soprano)
ウィーン国立音楽大学を卒業し、ウィーン舞台芸術とリート&オラトリオのディプロマを取得。キジアーナ音楽院でライナ・カバイヴァンスカに師事。「ホフマン物語」、「カプレーティとモンテッキ」、「フィガロの結婚」など、ヨーロッパ各地で多数のオペラに出演。また、オーストリア・シュタイアーのシューベルト音楽祭でオラトリオ「ラザロ」、ウィーン・コンツェルトハウスでオラトリオや独唱リサイタル等に出演。韓国に帰国後、「ドン・ジョヴァンニ」で韓国デビューを果たす。コンサート、ミサ曲、オラトリオなどで、韓国の数多くのオーケストラと共演している。